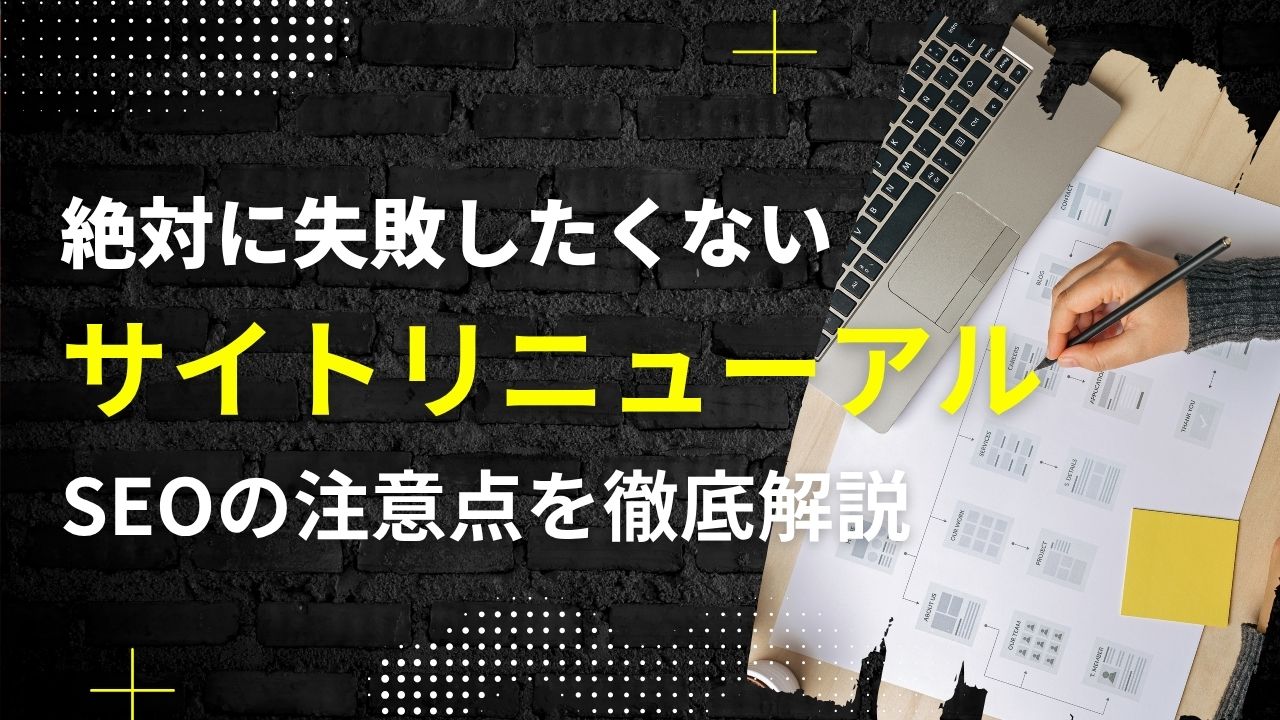サイトリニューアルは、デザインの刷新やUXの向上だけでなく、ビジネスの成長を加速させる絶好の機会です。
しかし中には、慎重なSEO対策を怠ったためにオーガニック流入が急減し、ビジネスに深刻なダメージを与えるケースも見受けられます。
本ガイドは、Web担当者およびWebサイト制作者の方々向けに、サイトリニューアルというプロジェクトを成功に導くための、技術的かつ戦略的なSEO対策を解説します。
単なる手順の紹介に留まらず、「なぜそれが必要なのか」という背景と、見落としがちな技術的要件まで踏み込みます。
リニューアルに伴うSEOリスクを最小限に抑え、検索順位を向上させるための具体的なアクションに繋がるように解説してまいります。
それではまず、リニューアルする上で欠かしてはいけない「SEOの注意点」について解説してきます。
リニューアルで意識すべき15のSEO注意点
サイトリニューアルは、デザインや機能を刷新する絶好の機会ですが、SEO対策を怠ると検索順位の大幅な低下を招く恐れがあります。
リニューアル時に必ず押さえるべき15のSEO注意点について、以下に詳しくまとめましたのでご一読ください。
①適切なリダイレクト処理
URL変更を伴うリニューアルでは、301リダイレクトの設定が最も重要です。旧URLが蓄積してきた評価を新URLに引き継ぐことができるため、検索順位の維持に直結します。
301リダイレクトを設定しないと、検索エンジンは新しいページを「全く別の新しいページ」として認識してしまいます。その結果、古いページが長年蓄積してきた検索順位や被リンクの評価がリセットされてしまい、順位の大幅な下落につながります。必ず、古いURLと新しいURLを1対1で対応させた301リダイレクトを設定しましょう。
具体的な対策
- すべての旧URLを新URLへ301リダイレクト設定
- 302や307などの一時的なリダイレクトは避ける
- リダイレクトチェーンを作らず、直接最終URLへ転送
- Google Search Consoleでアドレス変更ツールを活用
②内部リンクの削除に気をつける
内部リンクはサイト構造を検索エンジンに伝える重要な要素です。重要なページへのリンクを削除すると、そのページの評価が下がる可能性があります。
「内部リンク」は、ユーザーの回遊性を高めるだけでなく、検索エンジンがサイトの構造を理解し、各ページの重要度を判断するためにも重要な役割を担っています。
リニューアルの際にページを削除したりURLを変更したりすると、意図せず内部リンクが切れてしまうことがあります。リンク切れはユーザー体験を損なうだけでなく、検索エンジンのクローラーがサイト内を巡回できなくなる原因にもなります。リニューアル後は、リンク切れチェックツールなどを使って、切れているリンクがないか必ず確認し、修正しましょう。
具体的な対策
- 重要ページへの内部リンクは維持または増強
- 削除するリンクがSEO上重要でないか事前に確認
- パンくずリストやグローバルナビゲーションの見直し
- アンカーテキストも適切に最適化
③ディレクトリ構造の整備
ディレクトリ構造(URLの構造)は、シンプルで分かりやすいことが理想です。論理的で分かりやすいディレクトリ構造は、ユーザーにも検索エンジンにもサイトの階層を明確に伝えます。深すぎる階層は避け、シンプルな構造を目指しましょう。
現状のURLが、複雑で分かりにくいディレクトリ構造になっている場合は、リニューアルを機に論理的でシンプルな構造に見直すことを検討しましょう。
具体的な対策
- 3階層以内に重要ページを配置
- URLは意味のある単語で構成
- カテゴリ分けを論理的に整理
- 階層が深すぎる場合は構造を見直す
④コンテンツを削除し過ぎない
「デザインを刷新するために、古いコンテンツは思い切って削除しよう」と考えるのは危険です。たとえ古くても、アクセスを集めているページや、多くの被リンクを獲得しているページは、サイトにとって重要な資産です。
これらのページやコンテンツを安易に削除すると、サイト全体の評価を損なう可能性があり、トラフィックを損失する場合があります。
リニューアル前にGoogleアナリティクスなどで各ページのアクセス状況を確認し、重要なコンテンツは残すか、関連性の高いページへ移設するなどの対応をとりましょう。
具体的な対策
- Google Analyticsで各ページの流入数を確認
- 削除前に統合や改善の可能性を検討
- 価値のあるコンテンツは残す
- 削除する場合は適切なリダイレクト処理を実施
⑤ページ削除には気をつける
ページ削除は、そのページが持つSEO評価を失うことを意味します。情報が古くなった、サービスが終了したなどの理由でページを削除する場合は慎重な判断が必要です。
そのページが検索流入や被リンクを獲得している場合、削除することでサイト全体の評価に悪影響が及ぶ可能性があります。
具体的な対策
- 被リンク状況をツールで確認
- 削除せず統合できないか検討
- やむを得ず削除する場合は410ステータスか301リダイレクト
- ユーザーニーズがあるページは残す判断を
⑥title/descriptionの設定
titleタグとmeta descriptionは検索結果に表示される重要な情報です。適切に設定することでCTR(クリック率)向上とSEO効果が期待できます。
またtitleにキーワードが含まれているかなどもSEOの評価に影響します。
リニューアルの際、これらmetaタグの設定が消えてしまったり、異なるページで同じtitle/descriptionになってしまったりしないよう注意が必要です。SEOキーワードを意識しながら各ページの内容を的確に表し、ユーザーがクリックしたくなるような、ユニークなtitleとdescriptionを設定し直しましょう。
具体的な対策
- 各ページ固有のtitleを30文字前後で設定
- descriptionは120文字前後で魅力的に記述
- 主要キーワードを自然に含める
- 重複するtitle/descriptionは避ける
⑦適切なcanonical設定
重複コンテンツは検索エンジンの評価を分散させます。canonical設定により、正規URLを明示し、評価の集約が可能になります。
例えば、PC用とスマートフォン用でURLが異なる場合や、パラメータによって同じコンテンツが表示される場合などに使用します。この設定を間違えると、本来評価されたいページがインデックスされなくなる可能性があります。リニューアル後も、重複コンテンツが発生する箇所にはcanonicalタグを正しく設定しましょう。
具体的な対策
- URLパラメータがある場合は正規URLを指定
- 類似ページには適切なcanonicalタグを設置
- 自己参照canonicalも忘れずに設定
- HTTPSとHTTPの統一確認
⑧UIUXを意識
Googleはユーザー体験を重視しており、使いやすいサイトほど評価される傾向があります。直帰率や滞在時間などの行動指標もSEOに影響します。
使いにくいサイトや、情報が見つけにくいサイトは、ユーザーがすぐに離脱してしまいます。高い直帰率や短い滞在時間は、検索エンジンに「ユーザーにとって価値の低いサイト」と判断され、検索順位の低下につながる可能性があります。見た目のデザインだけでなく、ユーザーが目的をスムーズに達成できるか、という視点を常に持って設計しましょう。
具体的な対策
- 直感的なナビゲーション設計
- 読みやすいフォントサイズと行間
- 適切な余白とレイアウト
- CTA(行動喚起)ボタンの明確化
⑨モバイルフレンドリー対応
Googleはモバイルファーストインデックスを採用しており、サイトがモバイル端末に最適化されているか(モバイルフレンドリーであるか)は、SEOの必須要件です。モバイル端末での快適な閲覧は、SEOだけでなくUIUXにおいても非常に重要なポイントです。
レスポンシブデザインなどを採用し、スマートフォンでも文字が読みやすく、ボタンが押しやすいなど、快適に閲覧・操作できるサイトを構築しましょう。
具体的な対策
- レスポンシブデザインの実装
- タップ要素のサイズと間隔を適切に
- テキストサイズは読みやすく調整
- Google Mobile-Friendly Testでチェック
⑩サイトスピードの改善
ページ表示速度は、ユーザー体験と直接的なランキング要因の両面でSEOに影響します。特にモバイル環境では速度が重視されます。
表示が遅いサイトはユーザーの離脱率を高めるだけでなく、Googleもページの評価を下げる要因としています。
画像のファイルサイズを圧縮する、不要なコードを削除する、ブラウザのキャッシュ機能を活用するなど、ページの表示を高速化するための施策を積極的に行いましょう。Googleの「PageSpeed Insights」などのツールで自サイトの速度を計測できます。
具体的な対策
- 画像の圧縮と最適化(WebP形式の活用)
- 不要なJavaScript/CSSの削除
- ブラウザキャッシュの活用
- CDNの導入検討
- Core Web Vitals指標の改善
⑪404エラーページの適切な処理
ユーザーがアクセスしようとしたページが存在しない場合に表示されるのが「404エラーページ」です。デフォルトの簡素なエラーページが表示されるだけでは、ユーザーは「サイトが壊れているのかも」と感じ、そのまま離脱してしまいます。
サイトのデザインに合わせたオリジナルの404ページを作成し、「お探しのページは見つかりませんでした」というメッセージと共に、サイトのトップページへのリンクやサイト内検索フォームなどを設置することでユーザーの離脱を防ぎ、他のページへ誘導することができます。
具体的な対策
- カスタム404ページを用意し、サイト内へ誘導
- 404エラーの発生状況をSearch Consoleで監視
- 外部からリンクされている404ページは301リダイレクト
- 意図的な404は問題ないが、大量発生は要対処
⑫noindexの適切な処理
noindexタグは、特定のページを検索エンジンのデータベースに登録(インデックス)させないようにするためのメタタグです。内容の薄いページや、サイト内検索の結果ページなど、検索結果に表示させる必要のないページに使用します。
誤ったnoindex設定は重要ページをインデックスから削除してしまい、検索流入が完全に失われる致命的なミスとなります。
リニューアル時に注意したいのが、開発段階でテスト環境を検索エンジンにインデックスさせないためにサイト全体にnoindexを設定し、本番公開時にそれを解除し忘れるというミスです。これをやってしまうと、サイト全体が検索結果から消えてしまうため、公開前には必ず確認しましょう。
具体的な対策
- リニューアル前のnoindex設定を必ず解除
- 重要ページにnoindexが付いていないか確認
- テスト環境のnoindexを本番環境に持ち込まない
- Search Consoleでインデックス状況を監視
⑬外部リンクの確認と修正
外部サイトへのリンク切れはユーザー体験を損ない、サイトの信頼性を低下させます。また、重要な外部リソースへのリンクは情報価値を高めます。
サイトリニューアルでURLが変更になった場合、せっかく獲得した被リンクがリンク切れになってしまい、その評価を受け継ぐことができなくなります。
もちろん、301リダイレクトを設定していれば評価は引き継がれますが、可能であれば、リンク元のサイト管理者に連絡を取り、新しいURLへリンクを修正してもらうのが最も確実で丁寧な対応です。
具体的な対策
- リンク切れチェックツールで全体を確認
- 切れたリンクは削除または更新
- 低品質サイトへのリンクは見直す
- nofollowの適切な使用を検討
⑭XMLサイトマップの更新
XMLサイトマップは検索エンジンにサイト構造を伝え、効率的なクロールを促進します。
リニューアルによってページの追加・削除・URLの変更などが行われたら、必ずXMLサイトマップの内容も最新の状態に更新し、Googleサーチコンソールなどから再送信しましょう。
具体的な対策
- 新しいURL構造に基づいてサイトマップを生成
- 削除ページは除外し、新規ページは追加
- Google Search Consoleに送信
- 更新頻度や優先度を適切に設定
⑮robots.txtの適切な設定
robots.txtの誤った設定は、サイト全体や重要ページのクロールをブロックしてしまう可能性があります。リニューアル時には特に注意が必要です。
noindexと同様に、リニューアルの開発中にテストサイトへのクロールを拒否する設定を行い、本番公開時にその設定を戻し忘れるケースが散見されます。Disallow: / という記述が残っていると、クローラーがサイト全体を巡回できなくなり、インデックスに深刻な問題が生じます。公開前に必ずrobots.txtの内容を確認しましょう。
具体的な対策
- 重要ページがブロックされていないか確認
- テスト環境用の設定を本番に持ち込まない
- 不要なディレクトリのクロールは制限
- robots.txtテスターで動作確認
リニューアルで失敗しないための進め方
第1章:計画・準備フェーズ ─ リニューアルの成否を分ける重要段階
リニューアルの成功は、デザイン・コーディング・開発などのサイト制作が始まる前の「計画と準備」で9割が決まるといっても過言ではありません。この準備段階での分析と戦略設計が、開発段階や公開時に失敗を防ぐとても重要なファクターとなります。
1. 現状分析とSEO資産の棚卸し
まず最初に、既存サイトが持つ「SEO資産」を正確に把握します。既存サイトが持つSEO資産を毀損してしまうと、サイトの検索順位やオーガニック流入に悪影響を及ぼします。これらはリニューアル後も絶対に失ってはならない財産とも呼べるべきものです。
流入キーワードと重要ページの特定
Google Search Console (GSC) の「検索パフォーマンス」レポートから、過去12ヶ月間でクリック数・表示回数が多いクエリとページをすべてエクスポートします。これにより、ビジネスに貢献しているコアなページ群が明確になります。
次にGA4のランディングページレポートからセッション数が多い順、キーイベントが多い順のそれぞれのデータをエクスポートします。これによりアクセスを稼いでいるページとコンバージョンに貢献しているページが明確になります。
被リンク資産の評価
AhrefsやMajestic、SEMrushといった外部ツールを使用し、被リンクを受けているページを洗い出します。特に、ドメインオーソリティの高いサイトからのリンクは最重要資産です。URLが変更になる場合は、これらのページからの301リダイレクトが必須となります。また被リンクを受けているページをリニューアルの際に削除してしまわないように細心の注意を払わなければいけません。
パフォーマンスの分析
全ページのURLリストを作成し、Google Analytics (GA4) のセッション数、エンゲージメント、コンバージョン数、GSCの検索パフォーマンスデータを紐付けます。これにより、各コンテンツを「維持・強化(Keep/Improve)」「統合(Consolidate)」「削除(Delete)」の3つに分類します。トラフィックがほぼ無く、インデックスもされていない低品質なコンテンツは、思い切って削除・noindex化することもSEO評価の向上に繋がります。低品質なコンテンツを削除することで検索ロボットの回遊性(クローラビリティ)が向上し、SEOに好影響を与えるからです。ただし、低品質なページ以外のコンテンツを大量に削除することはSEOにおいて順位を下げてしまうリスクを伴います。
何を残して何を削除すべきか、正確な見極めが必要です。
2. 新サイトのURL構造とディレクトリ設計
URLの変更はSEO評価を下落するリスクを伴います。例えば「リダイレクト設定を忘れてしまった」「リダイレクト前とリダイレクト後のページ内容に大きな乖離がある」など不適切な対応を取ると、既存サイトのSEO評価を正確に引き継げず、サイトのSEO評価を落とすことになります。
そのため、リニューアル時に「URL変更によるメリットがあるか否か」を確認し、メリットがある場合に限って変更した方が良いでしょう。
では、メリットのあるURL変更とはどのようなケースがあるかご説明していきます。
URL設計の基本
- シンプルで予測可能か: example.com/category/service-a のように、ユーザーやクローラーが構造を理解しやすい形式が理想です。意味のないパラメータやセッションIDは含めないようにします。
- 恒久性: 一度決めたURLは、可能な限り変更しない前提で設計します。
- HTTPSの徹底: 全ページをHTTPSで統一します。
ディレクトリ階層の最適化
- 重要なページほどルートディレクトリに近い、浅い階層に配置します。深すぎる階層はクローラビリティを損なう可能性があります。
- 論理性:URL構造が整理されていると、クローラがサイトの階層や関連性を正しく理解しやすくなります。内部リンクの流れも明確になり、サイト全体のSEO効果を高められます。
例えば家電を販売するECサイトであれば、” /refrigerator/prduct-name/”のようにカテゴリと商品が親子構造になるように設計しましょう。
URL変更に伴うマッピング
- URLを変更する場合は、「旧URL」と「新URL」の全ペアをリスト化したマッピングシート(リダイレクトリスト) を必ず作成しましょう。
リスト化して301リダイレクトを行うことで、ページ評価や被リンク評価を適切に引き継ぐことができます。
URLはWebページを特定する住所のようなものです。リニューアルを機に、論理的で拡張性の高い構造に再設計しましょう。
第2章:設計・開発フェーズ ─ 技術的SEO要件の実装
計画フェーズで立てた戦略を、技術的に正しく実装する段階です。エンジニアとの密な連携が不可欠となります。
1. クローラビリティとインデクサビリティの確保
Googlebotがサイトを効率的に巡回し、正しく内容を理解できる状態を担保します。
robots.txtの適切な設定
- テスト環境: 開発中は、テスト環境がインデックスされないよう、必ずrobots.txtで全ユーザーエージェントを拒否(Disallow: /)し、Basic認証やIP制限をかけましょう。
- 本番環境: 公開と同時に、クロールを許可する設定に切り替えます。CSSやJSファイルへのクロールを拒否すると、レンダリングに支障をきたし評価が下がる可能性があるため、原則として許可します。テスト環境で拒否したユーザーエージェントの拒否を許可する(Allow: /)に変更するのを必ず忘れないようにしましょう。
XMLサイトマップの最適化
ページの最終更新日を示す <lastmod> タグは、コンテンツを実際に更新した場合のみ日付を変更してください。全ページの<lastmod>を安易に更新すると、Googleからの信頼性を損なう可能性があります。
大規模サイトの場合は、インデックスサイトマップ(複数のサイトマップを束ねるファイル)を利用して管理を効率化します。画像サイトマップや動画サイトマップも必要に応じて生成します。
JavaScriptフレームワーク(React, Vueなど)利用時の注意
クライアントサイドレンダリング(CSR)のみに依存すると、Googlebotがコンテンツを完全にレンダリングできず、SEOに不利になる可能性があります。サーバーサイドレンダリング(SSR)やスタティックサイトジェネレーション(SSG)を導入し、クローラーが初回アクセスでHTMLを完全に取得できる状態を確保することが強く推奨されます。
2. ページエクスペリエンスと内部リンクの最適化
ユーザー体験の質は、今や直接的なランキング要因です。
Core Web Vitals (CWV) の改善
- LCP (Largest Contentful Paint): 2.5秒未満を目指します。画像サイズの最適化(WebP形式の利用や容量の削減)、サーバーの応答速度(TTFB)の改善が鍵です。
- INP (Interaction to Next Paint): 200ミリ秒未満を目指します。不要なJavaScriptの実行を遅延・削除し、メインスレッドのブロッキングを防ぎます。
- CLS (Cumulative Layout Shift): 0.1未満を目指します。画像や広告には必ずwidthとheight属性を指定し、コンテンツが後から挿入されてレイアウトがずれるのを防ぎます。
内部リンク戦略
重要なページ(収益に繋がるページなど)へ、関連性の高いページから内部リンクを集めます。トピッククラスターモデルを意識して内部リンクを構成できると尚良いです。
フッターやサイドバーからの機械的なリンクだけでなく、本文中から文脈に合ったアンカーテキストでリンクを張ることが重要です。
パンくずリストは必ず設置し、BreadcrumbListの構造化データでマークアップしましょう。
3. メタタグと構造化データの高度な実装
検索エンジンに対して、ページの情報をより正確に伝えます。
canonicalタグの正しい利用
パラメータ付きURLやABテスト用の別URLなど、重複コンテンツが発生する可能性がある場合は、正規化したいページのURLをcanonicalタグで指定します。自己参照(自分自身のURLをcanonicalに指定)も基本的には記述します。
hreflangタグの実装(多言語サイトの場合)
言語や国ごとにページが分かれている場合、hreflang属性で各ページの対象言語・地域を明示し、相互にリンクさせます。これにより、適切なユーザーに適切な言語のページが表示され、重複コンテンツ評価を避けることができます。
構造化データ(Schema.org)の実装
JSON-LD形式での実装を推奨します。記事(Article)、製品(Product)、よくある質問(FAQPage)、組織情報(Organization)など、コンテンツのタイプに合わせて適切なスキーマを選択し、詳細な情報をマークアップすることで、リッチリザルト表示の可能性が高まります。
第3章:公開(ローンチ)前後の最終チェックとモニタリング
いよいよ公開です。ここでのミスは致命傷になるため、細心の注意を払いましょう。
1. ローンチ直前の最終検証(ステージング環境)
本番公開前に、テスト環境で以下の項目を「指差し確認」で検証します。
リダイレクトの検証
作成したリダイレクトリストに基づき、旧URLにアクセスした際に、意図した新URLへステータスコード301でリダイレクトされるかを全件チェックします。Screaming Frog SEO Spiderのようなクローラーツールでリストを読み込ませると効率的です。リダイレクトチェーン(A→B→C)が発生していないかも確認します。
メタタグ設定の最終確認
「title」「 meta description」「canonical」「 meta robots (index, followになっているか) 」などのメタタグが正しく設定されているか。目視で最終チェックします。
GA4 / GTMなどの計測タグが正しく設置されているか。
GA4またはGTMのタグ設置を忘れていないか、これも目視で必ずチェックしておきましょう。
設定が外れていると解析データの連続性が途切れてしまい、リニューアル前後の変化を正確に分析することが難しくなります。
2. ローンチ当日〜翌日のタスク
- DNSやドキュメントルートを切り替え、新サイトを公開。
- Basic認証やIP制限を解除。
- robots.txtを本番用に差し替え、クロールを許可する。 (最重要)
- サーチコンソールでXMLサイトマップを送信する。
- サーチコンソールの「URL検査ツール」から、トップページおよび主要なページのインデックス登録をリクエストする。
- サーチコンソールで「アドレス変更ツール」を使用する(ドメイン変更の場合のみ)。
3. 公開後の効果測定と改善
公開後、最低でも1〜3ヶ月は以下の指標を定点観測します。
GSCでの監視
インデックスカバレッジ:「エラー」「除外」が増えていないか毎日確認。特に404エラーの急増はリダイレクト漏れのサインです。
検索パフォーマンス: 旧サイトと比較し、クリック数・表示回数・平均順位の変動を注視します。特に順位が下落傾向にある場合は要注意です!
GA4でのトラフィック分析
チャネル別の流入、特に「Organic Search」のセッション数が急落していないかを確認します。
順位変動のモニタリング
リニューアル後は、検索順位の変動が起きやすいため、定期的にモニタリングし、必要に応じて調整を行います。GRCなどの順位チェックツールで、対策キーワードの順位変動をデイリーで追いかけます。
特に下落傾向が続く場合は、適切な対応が必要です。
以下のようなポイントをチェックし、早急な対応を心がけましょう。
- リダイレクトにミスはないか
- コンテンツを削除し過ぎていないか
- 内部リンクに問題はないか
- robots.txtに問題はないか
- GSCのインデックスレポートで重大なエラーが出ていないか
特に大幅な下落があった場合は、何かしらの致命的なミスを起こした可能性があります。迅速に問題に取り掛かりましょう。
弊社では、リニューアルのSEO復活支援も行っております。問題が分からない場合は、お問い合わせください。
まとめ
サイトリニューアルは、SEOにとって諸刃の剣です。適切な対策を講じれば検索順位を維持・向上できますが、注意を怠ると大きな損失を招きます。
SEOの注意点15項目を必ずチェックし、適切なリニューアルを心がけましょう。不安な場合は、弊社のようなSEOの専門会社に相談することも成功への1つの手段です。
リニューアル後の数ヶ月間は検索順位やトラフィックを注意深く監視しましょう。何かあれば迅速に問題解決へ取り掛かることが機会損失を防ぐことにつながります。
この記事が、皆様の重要なサイトリニューアルプロジェクトを成功に導く一助となれば幸いです。