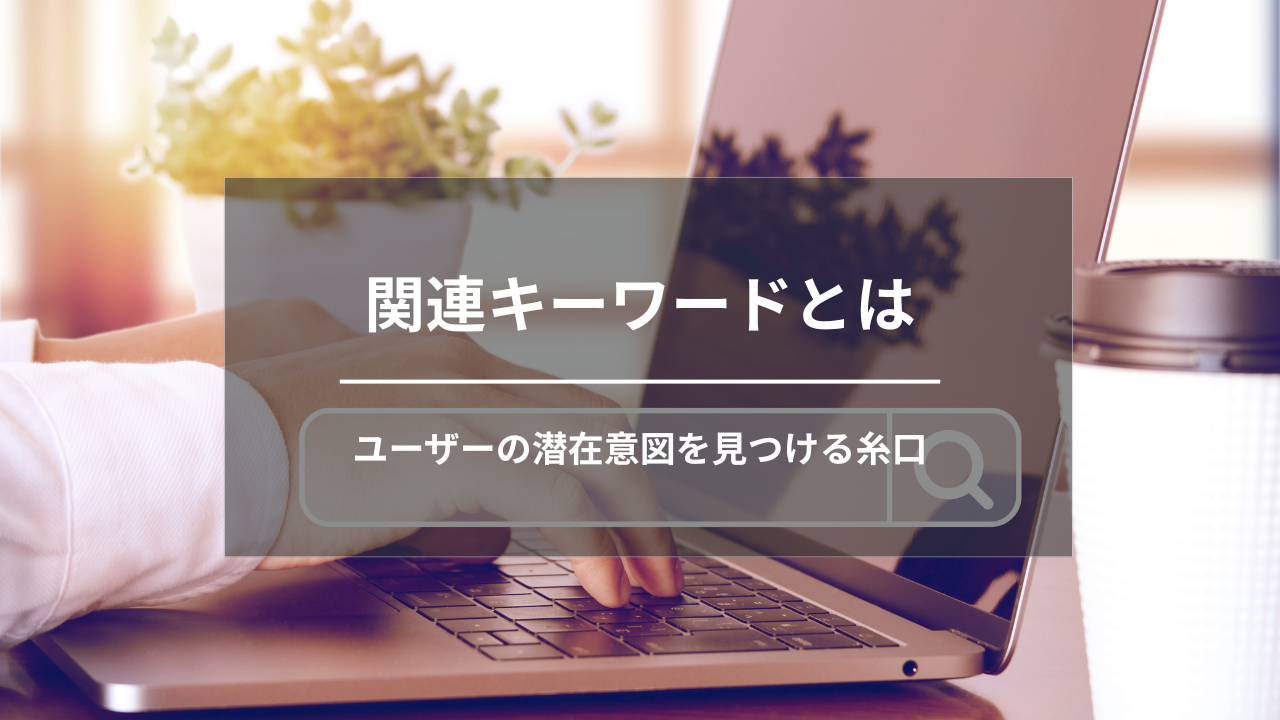「関連キーワード」は、SEO対策やコンテンツ制作において、ユーザーの「潜在的な検索意図(インサイト)」を読み解くための最も重要な手がかりの一つです。
しかし、多くのWeb担当者が「サジェストキーワード」や「共起語」と混同しており、その真価を十分に活用できていないケースが散見されます。
あなたは今、このような疑問や勘違いを抱えていませんか?
- 「サジェストキーワードと何が違うの?」
- 「ただ本文中にキーワードを散りばめれば良いと思っている」
- 「ラッコキーワードで出てきた言葉を、何も考えずに全部使っている」
結論から言えば、関連キーワードとサジェストキーワードは、全く別の役割を持っています。 サジェストが「検索の入り口(入力支援)」であるのに対し、関連キーワードは「検索の出口(再検索行動)」、つまりユーザーが最初の検索で満足できずに「次に知りたくなった情報」そのものだからです。
この本質を理解せず、ただツールで抽出した単語を羅列するだけでは、現在のGoogleアルゴリズムで上位表示を勝ち取ることはできません。逆に言えば、関連キーワードを正しく分析できれば、ユーザーさえ気づいていない「潜在ニーズ」を先読みした、質の高いコンテンツを作ることができます。
この記事では、SEOの現場で多くのサイトを改善してきた知見をもとに、関連キーワードの正確な定義から、Googleのアルゴリズムにおける仕組み、そして検索順位を上げるための具体的な活用メソッドまでを専門的な視点で解説します。
目次
関連キーワードとは?(定義と仕組み)
関連キーワード(Related Keywords)とは、Googleなどの検索エンジンの検索結果ページ(SERPs)の最下部などに表示される、「そのキーワードを検索したユーザーが、次に検索する可能性が高いキーワード群」のことです。
Google検索では「他の人はこちらも検索(People also search for)」や「関連性の高い検索」として表示されます。
なぜ表示されるのか?(アルゴリズムの仕組み)
関連キーワードは、単なる語句の組み合わせではなく、膨大なユーザー行動データに基づいて生成されています。
主に以下の2つの要素が影響しています。
- 再検索(Re-search)のデータ:
あるキーワードで検索したユーザーが、求めている情報が見つからずに、その直後に検索し直したキーワードデータ。
つまり、あるユーザーが「A」というキーワードで検索した後、求めている情報が見つからず、直後に「B」というキーワードで検索し直した場合、Googleは「AとBには強い関連がある」と学習します。 - 意味的な関連性(Semantic Relevance):
検索されたメインキーワードと、文脈的・意味的に深いつながりがあるトピック(共起関係にある概念など)が表示されます。
つまり、関連キーワードは「ユーザーが最初の検索で満たされなかったニーズ」や「次に知りたくなる情報」をGoogleが先回りして提示している「情報の補完リスト」と言えます。
【図解】関連キーワード・サジェスト・共起語の決定的な違い
SEO初心者が最も混同しやすいのが、「サジェストキーワード」や「共起語」との違いです。
これらは役割も、SEOでの活用シーンも全く異なります。以下の表で整理しました。
| 比較項目 | サジェストキーワード | 関連キーワード | 共起語 |
| 表示場所 | 検索窓(入力中) | 検索結果の最下部など | 検索画面には出ない (上位サイトの本文中) |
| 生成要因 | 検索ボリュームトレンド 入力履歴 | 再検索された言葉 文脈的つながり | 上位ページ内で頻出する単語 |
| ユーザー心理 | 「入力が面倒」 「みんなは何と調べてる?」 | 「情報がなかった」 「もっと深く知りたい」 | (ユーザーは意識しない) Googleが内容理解に利用 |
| SEO活用 | キーワード選定 (記事テーマの決定) | 記事構成案 (見出しの作成) | 本文の執筆 (専門性の補強) |
1. サジェストは「入り口(入力支援)」
サジェストは検索ボリューム(人気度)や直近のトレンドに強く影響されます。「多くの人がいま検索している言葉」を知るための指標です。
2. 関連キーワードは「出口(情報の深掘り)」
関連キーワードは、検索行動の「結果」として表示されます。ユーザーがそのトピックについて深く知ろうとした軌跡であるため、記事の**「網羅性」**を高めるための構成案作りに役立ちます。
3. 共起語は「専門性(語彙力)」
共起語は、そのテーマを語る上で自然と使われるべき言葉(例:「スマホ」の記事なら「アプリ」「バッテリー」「画面」など)です。これは見出しにするというより、本文ライティングの際に自然に盛り込むことで、Googleに専門性を伝えます。
関連キーワードを調べる方法・代表的なツール
正確な関連キーワードを抽出するための代表的な方法とツールを紹介します。
1. Google検索結果(「他の人はこちらも検索」)
最も基本的かつ確実なソースです。
- PC版: 検索結果の最下部に「関連する検索キーワード」として表示されます。
- スマホ版: 検索結果の途中に「他の人はこちらも検索」としてアコーディオン形式で挿入されることが多いです。
2. ラッコキーワード(旧:関連キーワード取得ツール)
日本のSEO・コンテンツ制作者の代表的な関連キーワード取得ツールです。
ラッコキーワードサイトの検索窓にキーワードを入れるだけで、「Googleサジェスト」「関連キーワード(再検索ワード)」「Q&Aサイト」などを一括で取得できます。 特に「再検索ワード」のタブを見ることで、より深いユーザーインサイトに触れることができます。
- 特徴: Googleサジェスト、関連キーワード(再検索ワード)、教えて!gooなどのQ&Aサイトの質問を一括で取得可能。
- 活用法: 「再検索ワード」のタブを見ることで、より深いユーザーニーズを拾えます。
3. Googleキーワードプランナー
抽出した関連キーワードの中で、「実際にどれくらい検索ボリューム(需要)があるのか」を確認するために使用します。
- 特徴: キーワードの検索ボリュームと競合性を確認できます。
- 活用法: 抽出した関連キーワードの中で、特に月間検索ボリューム(需要)があるものがどれかを判断する際に使用します。
SEOで順位を上げる!関連キーワードの活用3ステップ
単に関連キーワードを本文中に散りばめるだけでは、現在のSEOでは評価されません。以下のように、「構成(ストラクチャ)」に反映させる必要があります。
STEP 1: 検索意図(インサイト)のグルーピング
ツールで抽出した関連キーワードを、そのまま使うのではなく「ユーザーの意図」ごとに分類します。
例:「クレジットカード おすすめ」の関連キーワードの場合
- 【属性】グループ: 「学生」「主婦」「公務員」
- 【条件】グループ: 「年会費無料」「還元率」「審査甘い」
- 【不安】グループ: 「デメリット」「作り方」
似たような意図のキーワードは一つにまとめ、情報の重複を防ぎます。
STEP 2: 見出し(H2・H3)への採用
分類したグループをもとに、記事の見出しを作成します。関連キーワードは「ユーザーが次に知りたいこと」であるため、これらを網羅することで「検索者が再検索する必要のない(1記事で完結する)高品質なコンテンツ」と評価されます。
- 悪い例: 本文中に無理やりキーワードを詰め込む(キーワードスタッフィング)。
- 良い例: H2見出しとして「主婦におすすめのクレジットカード」や「還元率で選ぶ際の注意点」を設定し、章立てて丁寧に解説する。
STEP 3: 潜在ニーズへの先回り回答
関連キーワードには、ユーザー自身も言語化できていない「潜在的な悩み」が含まれます。
例えば「関連キーワードとは」で検索する人の関連キーワードに「表示されない」があった場合、「関連キーワードの意味を知りたい」だけでなく、「自分のサイトで表示されないトラブルを解決したい」という深層的な悩みやニーズを持っている可能性があります。
記事の後半にこのトラブルシューティングを含めることで、ユーザーの満足度が向上し、滞在時間の延長(=SEO評価の向上)につながります。
関連キーワード対策の注意点(やってはいけないこと)
SEO効果を狙うあまり、過剰な対策が逆にSEO評価を下げることもあります。以下の行為を行うとGoogleからペナルティを受ける、または評価を下げるリスクがあります。
キーワードスタッフィング(詰め込み)
文脈を無視して関連キーワードを羅列したり、隠しテキストで入れたりする行為は、Googleから「キーワードスタッフィング」とみなされ、ペナルティの対象になる可能性があります。あくまで「読者にとって自然な文脈」で使うことが大前提です。
無関係なキーワードの含有
検索ボリューム欲しさに、記事のテーマと関連性の薄いキーワードを見出しに入れると、専門性が薄まり、全体の評価が下がります。
情報の重複(カニバリゼーション)
1つの関連キーワードに対して、別々の記事を量産することで、サイト内で情報の重複(カニバリゼーション)が起き、互いに評価を食い合ってしまうことがあります。関連キーワードはあくまで「メインテーマを補完する要素」として、1つの記事内で網羅する方が現在は評価されやすい傾向にあります。
まとめ:関連キーワードは「ユーザーへの回答」そのもの
関連キーワードとは、Googleが提示する「ユーザーが満たされなかったニーズのリスト」です。
- サジェストは「入力支援」、関連キーワードは「ニーズの深堀り」。
- ツールを使って網羅的に取得し、検索意図ごとにグルーピングする。
- 見出し構成に反映させ、再検索させない「完結型コンテンツ」を作る。
これらを意識してコンテンツを作成することで、ユーザーにとってもGoogleにとっても価値のある記事を作ることができます。
関連キーワードは、Googleがこっそり教えてくれている「ユーザーが本当に知りたがっていることリスト」に他なりません。 このリストを一つひとつ丁寧に紐解き、記事構成に反映させることで、あなたの記事は「他のサイトを見る必要がない、1記事で完結する最強のコンテンツ」へと生まれ変わります。
ぜひ今日から、単なるキーワードの詰め込みを卒業し、関連キーワードに基づいた「ユーザーファーストな記事作り」を実践してみてください。